こんにちは、猫は天使と思っている大福です。
大福は、12歳と13歳になる2匹の猫(&子供ちゃん)と暮らしています。
1匹目との出会いは、独身当時住んでいたマンションの下に突然現れました。
きれいな猫で人なつっこかったので、迷い猫か捨て猫だろうと思い1週間ほど様子を見ていたのですが、誰も保護する様子もなくご飯をもらえている様子もなく、それでも毎日マンションの下に現れるので心配していました。
1週間経った頃、猫はマンションの住人に追い払われてしまい、そこからパッタリと現れなくなりました。季節は夏で、そろそろなんとかしないと命の危険もあると思った大福は、次に猫に会ったら保護しようと決意。
更にその1週間後に、すっかり薄汚れて痩せた姿で猫はマンションにひょっこりと現れました。
タイミングよく猫を抱っこすることが出来たので、そのまま部屋の中に連れて帰ったのですが、部屋に入れた瞬間から大パニックを起こし、大声で鳴き叫び始めて玄関で暴れてしまったので、一旦開放し1回目の保護は大失敗。

抱っこで部屋に連れて帰るのは無謀だった…
怖い思いさせちゃった(反省)
すぐにキャリーケース購入して、更に猫が現れるのを待つことしました。…2日後だったかな。猫は無事にマンションに現れてくれました。
お腹がペコペコだったようで、キャリーケースの中にご飯を置くと、恐る恐る中に入っていきました。頭がすっかりケースに収まったタイミングでお尻をグイッと押して保護成功。その場でキャリーケースをタオルでくるみ連れて帰りました。
最初の方はやはり鳴き叫ぶので、当時ペット不可のマンションに済んでいた私はヒヤヒヤ。一晩中寝ないでキャリーケースの様子を気にしながら過ごしました。
翌日になると鳴き声もだいぶ落ち着いてきたので、ケースの扉を開けると猫はベッドの下に隠れていました。
元々飼い猫だったと思うので、1日も経てば室内にも慣れて、のびのびする姿を観ることができるように。
一方大福は、飼い主探しや引き取り手を探しに没頭です。

飼い猫で(去勢・避妊手術済の場合)、大体自宅から半径50~100m以内にいるといわれています。逃げ出してしまった自宅から、そんなに移動していない可能性が高い!
迷い猫か捨て猫か分からない時は、以下を参考にしてください!
⇒遺失物扱いになるので、飼い主が現れなかった時は引き取る旨を伝えてください(保健所に送られてしまいます)。
・保健所や動物愛護センターの迷い猫情報を毎日チェック
・近所の電柱や回覧板、動物病院の迷い猫の情報を見て回る
⇒必死に探している飼い主さんは、ほとんどの人が張り紙を出します
・猫を一時預かりできない場合は、預かり先を探す(病院やペットホテルはお金がかかります)
結果、どうやら探している人もいないし、引き取り手も見つかりません。
すっかり情もうつってしまっていた大福が飼うことになり、1ヶ月だけ知り合いの伝手で猫を預かってもらい、急いでペット可のマンションに引っ越したという経緯があります。

運命の出会いだったと思っていますー
ですが、その猫は、実はお留守番が出来ない子でした。大福が仕事で家を空けると不安になって粗相が酷くなってしまいました。

分離不安症の子に多い症状みたいです。あとは単にお留守番が嫌でクレームを出していたとも考えられます(めっちゃ大変だった)
毎日続く粗相に困ってしまい、孤独を嫌がっているように感じたので、思い切って2匹目を迎えることにしました。
2匹目の子は、里親サイトで探してお迎え。
すると、数日で粗相は治り、毎日仲良くしている姿でほっこりできるようになりました!
そんな2匹もすっかりシニア猫。
もう10年以上ともに暮らしてきているので家族です。
まだまだ長生きしてほしいと願うばかりですが、やはり人間同様、生老病死は猫にも出てきます。
13歳の子は心臓に疾患があり、12歳の子は膵炎などで2度ほど命が危ない状況にもなりました。
現在は落ち着き、薬は飲ませる必要があるものの、2匹とも元気に過ごしています。
今回は、猫と暮らしてきた大福なりに、高齢猫のお世話で大事なことをまとめてみました。
1.猫のシニアゾーンは何歳から?
猫は7歳すぎると中年ゾーンに突入します。人間年齢では44歳くらいです。まだまだ身体は元気ですが、すこしずつ病気の片鱗が見え隠れしてくる頃ですね。
11歳からはシニアゾーンとなります。人間年齢では60歳程度です。まだ元気に生きる年齢ではありますが、健康には一層気を使わないといけないお年頃になります。最近は医療の発達などから20歳くらいまで生きる猫も珍しくなくなってきました。

20歳は人間年齢では100歳くらい!
猫は生命力の強い生き物だって聞いたことがあります!
2.シニア猫は健康診断がマスト
できれば若い頃から毎年受けたいところですが、少なくとも10歳ごろからは毎年受けるようにしましょう。健康診断といっても、人間みたいに1日かけて身体を調べるとかではありません。
大体以下を見てもらえれば大丈夫だと思うものをリストにしました。大福の猫は高齢猫で病気持ちなので、数ヶ月に1回のペースで血液検査とエコーはやってもらっています。費用は目安で2万円/回程度です。
- 血液検査
血液検査では、猫に特に大事な臓器である肝臓や腎臓に関してわかります。 - 先生の触診(エコー含む)
外科的な面であれば、動物病院の先生が触診で大体分かりますし、エコーをやっておけば更に安心。触診の際に口内もしっかりチェックしてもらってください(歯の歯石や歯茎の炎症など)。 - 検便
猫にとってうんちは健康のバロメーターなので、うんちの異常は放置してはいけません。ただ、通常のコロコロしたうんちがででいる限りは検査はマストでなくても大丈夫です。うんちに関わらず、猫の排泄状況は常に把握して先生に伝えられるようにしましょう。
3.「知識経験のある」かかりつけ医を見つける
やりがちなのが「自宅近くの動物病院に連れて行く」ということ。
もちろん、若いうちの予防接種程度あれば、それでも問題はないのですが、高齢猫になってくると動物病院の先生のレベルも見極める必要があります。
正直、動物病院の先生って人間の先生以上にピンキリです。
「本当に動物が好きだから・病気の動物を助けたいから」という崇高な理由で先生をやっている人もいれば、単なる金儲けのためにやってる先生もいます。そこまで優秀じゃないけれど動物病院の開業医をしている人もかなりの数でいます。

人間でも同じことが言えますが、医師の良し悪しは飼い主がきちんと見極める必要があります。
大福家の2匹目の猫が10歳の頃、いきなりご飯も食べなくなり、ぐったりしだしたことがありました。
明らかに状態がおかしいので、すぐに自宅近くの動物病院に連れていくと「成猫は、たまにご飯を食べずに自分の身体の状態を整えることがあるから大丈夫」と言われて整腸剤だけ出されて終わりました。

こんな元気ないのに。なんだかおかしい気がする…
不安的中。帰宅後、更に状態が悪化し、嘔吐下痢が酷くなり全く動かなくなってしまいました。
急いで、以前のかかりつけの先生に聞いていた別の病院に駆け込んだところ、急性膵炎を起こしていて命が危険な状態だったことが判明しました。

紹介された病院がちょっと遠かったので、自宅近くの病院を選んでしまっていましたが猛烈に反省しました
医師のレベルによって、このようなことが普通に起きます。
1軒目の先生は悪気があったわけではなく、本当にそのレベルのことだと判断したのだと思います。この差は、先生の知識と経験の差でしかありません。
特に動物は、人間よりこういうケースが起きやすいと思います。
先生に言われたことを鵜呑みにせず、猫の状態がおかしいなら違う病院を積極的に探す姿勢が(高齢猫に限りませんが)必要です。
動物病院の先生はいい先生であればあるほど変わり者であることが多いと大福は思っていて、この先生も、声がすごく大きくてはじめは面食らいました。

本質的には根っからの動物好きな人で、わからないことは聞けばなんでも教えてくれて「家族」として暮らすベストな状態を一緒に考えてくれます
その代わりというほどでもないですが、病院代や通院の手間はかかりますが、仮にそれが自分の家族や子供だったら当たり前のことだなと思います(誤解のないように書きますが、診療費用は良心的な価格です。ぼったくりもなく、不必要な医療などは一切やりません)。
こちらの質問に真摯に対応してくれるかも大事です。
補足ですが、補助医療を拒む病院は避けましょう。
本来通っているかかりつけ医がいるけれど、病院が休診でもらえない時などに、一時的に違う病院に行ったとします。
「本来は〇〇病院で診てもらっているのですが、今日お休みで、でも具合が急変してしまったので診てほしい」と事情を説明した時に嫌な反応をする医者や病院はまともな病院ではありません。

大福は過去に一度だけ、そういう先生に当たったことがあります。
「どちらで通院をするのか決めてくれないと困る」と言われました。
補助医療であれ何であれ、命や健康を第一に考えてくれない先生は信用できません。
ちなみに、先生の自宅併設の病院だと休診の日も電話をしたら時間外診療に対応してくれるところもあります。大福家のかかりつけ医も自宅併設なので「なにかあったらすぐ電話して」って言われています。また、万が一に備え、夜間診療に対応してくれる病院も見つけておきましょう。
4.部屋の温度管理に気をつける
健康管理の上で、健康診断と病院探しの次に大事なのは日ごろからの維持管理です。
猫は室内飼いを徹底することは基本中の基本ですが、室内で飼う際に大事なのは、温度管理です。
猫は暑さに強いとか寒さに弱いとかいろんな諸説ありますが、正直室内で飼われている猫は暑さにも寒さにも弱いです。

猫だから大丈夫だろうという油断は大敵!
大福家の温度管理を書き出してみました。
夏の温度管理
- 猫の熱中症リスクを避けるため、家のエアコンは24時間つけっぱなし。
- 外出時は28℃「弱」や「しずか運転」で、レースのカーテンは締める。
- 猛暑日は、普通のカーテンも半分くらい締めておき日差しを防ぐ。
- 室内の体感温度が30℃程度であれば、猫は問題なく過ごせる。
冬の温度管理
- 在宅のうちに部屋を温め、自宅を出る際はエアコンを切る。
- 冬場は猫用にペットベッドを用意しておく(猫はだいたいそこで寝る)。
- 部屋の冷えが気になる日は、ペットベッドのクッションの下にホッカイロを入れる。
- 夏よりも冬のほうが、布団の中にもぐるなどで猫が好きに暖をとれるので、夏ほど神経質になる必要はない。
- 外出時はホットカーペットやエアコンはOFF。
夏も冬も、最低限の環境を整えてあげるというのが大事なポイントかなと思います。
ちなみに春とか秋とかの気候が良い季節には、風通し用の窓があるので、そこを開けて換気扇を回しておく程度で大福家は問題ありません。
5.食の嗜好性の変化に合わせてフードを見直す
若い頃は何でも食べる猫も、加齢によって食の好みが変わることも珍しくありません。

人間でも若い頃はこってりが大好きだったけど、歳をとるとあまり受け付けなくなったりしますよね!
大福家の猫も、特に1匹目が食にこだわりを見せるようになり、気に入らないものは全く食べなくなったため、現在ペットフードを色々変えて何だったら食べてくれるのかを試行錯誤しています。
現在は「なんでもいいから食べたがるものをあげていい」と言われているので、毎回ペットフードを変えるなど工夫しながら給餌しています。大福は「安い餌は”粗悪な材料”でできている」説を信じてプレミアムフードをあげるようにしていますが、先生の話では「よほどじゃない限り、今のペットフードはそこまで粗悪品でもないよ」と言っていました(ここは大福も現在勉強中です)。また、よく「シニア向け」とか「療法食」とかありますが、表記年齢にはあまりこだわらなくてもよく、シニアになったら第一は「なんでもいいから食べてくれるほうが大事」とのことです。
5.投薬と強制給餌をできるようにする
ペットを飼っている方で意外とできないのが、投薬と強制給餌。でもシニア猫になると看病で投薬と強制給餌が必要なシーンは普通に起こります。

点滴まで自分でやってしまう猫飼いマスターの人もいるほど!
薬をご飯に混ぜてあげる飼い主さんも多いと思います。
大福も昔はそれでしのいでいましたが、最近はご飯の味が変わってしまうと食べなくないので、経口投薬を病院で教えてもらって直接飲ませています。粉であれば、少しの水で溶いてスポイトを使って飲ませるのが早くておすすめです。
6.ひとりで落ち着ける空間を確保できるように配慮する
猫の性格にもよりますが、基本的に猫は気ままな性質の動物です。飼い主と一緒にいたい時は飼ってに近寄ってきますが、一人になりたい時は勝手にいなくなります。

猫が一人で落ち着ける空間があるかどうかはとても大事
部屋を用意するような必要はなく、例えば「テレビ裏は絶対に誰もこないからここは絶対安心」とか「押入れのこの一角は誰もこないからひとりで落ち着ける」とかのレベルで大丈夫です。
7.スキンシップを大切に、子供と同様に語りかけ愛情を伝える
実は、この飼い主とのコミュニケーションがシニア猫には一番大事だと思います。
猫も10年位生きていると人間の言葉がある程度わかっているという説もありますが、大福も本当だと実感しています。

もともとペットとして開発された動物が猫なので、猫も愛されたい動物ですよ
IKEAの面白い実験があります。
この実験をみても、植物でさえ反応がでるのだから、動物ならなおさらのことだなと思いませんか?
大福は、1日1回、猫を抱きしめながら「ありがとう」「大好きだよ」「愛してるよ」「長生きしてね」「一緒にいようね」っていうポジティブな声掛けするように心がけていて、10年以上続けています。

実は、猫を癒やしているつもりで自分も癒やされているんだよなぁ
そして、これがペットを飼うことの醍醐味なんだろうなとも思います。
この声掛けが実際にどの程度効果を出しているかは数値などでは出せませんが、少なくとも命の危険にまで陥った猫が2回も元気に回復してくれています。
先生も、危篤の時を見ているので、「ここまで良くなるの???」と、びっくりしていました。
だから、実はすごく効果があるんだろうと信じています。
猫も家族、人間と同じように考えて接してあげること
まとめになりますが、結局のところ「猫も人間と同じように生老病死がある。感情もある。だから人間と同じように愛してあげればいい」というのが実感するところです。
もし猫が自分の子供だったらどうするかなって思えば、病院探しや看病なども同じようにできるのではないでしょうか。
「猫だから」ではなく「猫だけど」という思考がシニア猫には特に大事になると思います。
少しでも愛しい家族に健康に長生きしてもらえるよう、工夫していきましょう!
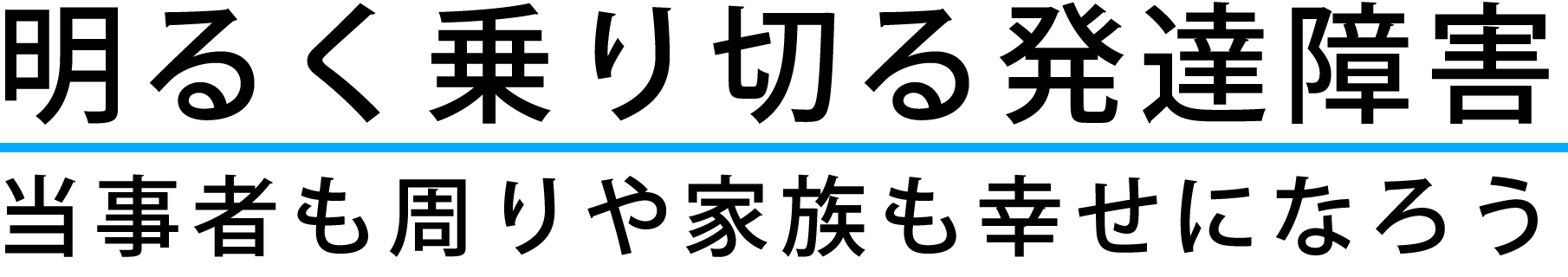



コメント