こんにちは、トイレが怖いと大泣きした子供に疲れ果てた大福です。
今回は、最近読んだ興味深い漫画があったので、紹介します!
「ケーキの切れない非行少年たち」原作 宮口幸治/漫画 鈴木マサカズ
原作著者は、児童精神科医の宮口幸治(みやぐち こうじ)先生。
発達障害・境界知能や軽度知的障害などに関する本を多く出版されています。
物語の舞台は少年院です。
非行少年たちの知能や発達問題に焦点をあてている作品で、軽度知的障害・境界知能者・発達障害を抱えている子が登場します。
実際に、少年院に入院してくる子のうち、発達障害・軽度知的障害・境界知能のあるケースの割合いが非常に高いことから、犯罪と発達障害・知的障害の根深さがわかる内容になっています。
知能の低い人の特性がわかりやすく描かれている
漫画の主人公である六麦(ろくむぎ)先生は精神科医です。
入院した少年・少女と六麦先生が面談をするのですが、初めての面談で少年・少女たちにも「ケーキを3等分してください」というテストをします。
勘のいい方はピンときたかもしれません。
そうです、このテスト、知能レベルを見極めるためのテストです。
知能に問題のある(軽度知的障害~境界知能)子は、ケーキの分け方に一定の傾向があります。
ケーキを均等にと思うと、ベンツマークのような切り方を想像するのが一般的ですが、少年たちはそれが思いつきません。

今度トレインにテストしてみます
また、テストの結果を見て六麦先生が「この子”も”か」と思うくらいの頻度で、知能問題を抱えている子は多く存在しているってことなんですよね。
更に、少年たちが犯罪に至るまでの経緯も作中で描かれているのですが、その描き方のリアルさよ!登場する少年たちは、軽度知的障害や境界知能でもIQ70台の子が多いのですが、元夫トレイン(IQ80台)にも同じ傾向がありありでしたね。
ちょっとネガティブな表現になっちゃいますが、あえて書くと軽度知的障害や境界知能の人が、
いかに
「認知が弱く」
それゆえに
「客観性がなく」
「自分のことがわからないか」
が、ひしひしと伝わってきました。
本人に頑張ろうという気持ちがないわけではなく、
むしろ頑張ろうと思うからこそ、うまくいかずに挫折し続けている。
成功体験がほとんどなく、社会に認められず、
失敗を繰り返しているから劣等感や被害者意識も強くなる。
そして、問題が起きると処理が追いつかずにパニックを起こす。
早い段階で適切な支援が受けられていたら、彼らは犯罪に手を染めずに済んだのだろうかと考えずにはいられない内容でした。
発達障害が加わってたとしたら、そりゃもう生きづらいの極みです。
(実際に発達障害と知能問題を併せ持っている少年も登場します)
犯罪に至るまでを表したピラミッドの図が出てくるのですが、
大福は首がもげるほどうなずきました。
ギリギリ境界知能の領域から出ましたが、
どうしていいかわからなくなると(処理が追いつかなくなると)
パニックを起こす流れはトレインも全く同じです。
基本構造はバッチリ当てはまってますので
今後もトレインには境界知能の対応をとるのが適切だなと改めて思い直しました。
むしろ、発達障害よりも知能問題のほうが問題行動の直接的なウェイトが大きかったのかも!とすら思います。
生きずらさの末に起こる犯罪行為
見逃せないのが、当人を取り巻く家庭や親子関係です。
家庭や親との関係に何かしらの問題を抱えているために、適切な支援を受けられず、
知能の低さによる生きづらさをちゃんと理解してもらえないまま育ち、
犯罪に至ってしまったというところまでも丁寧に描かれています。

子供の知能問題に気づけない親自身にも
知能問題があったりするんですよね…
なぜ自分の人生がこのようになってしまうのか分からず、解決することもできず、
根底には、うまく生きられないことによる劣等感やストレスが溜まっています。
でも、そのストレス自体も「自覚」できなかったりする。

コップの水があふれかえっていても、注がれる水を止められない
水の勢いを緩める方法もわからない。
なぜコップの中に水が注がれているのかわからない…
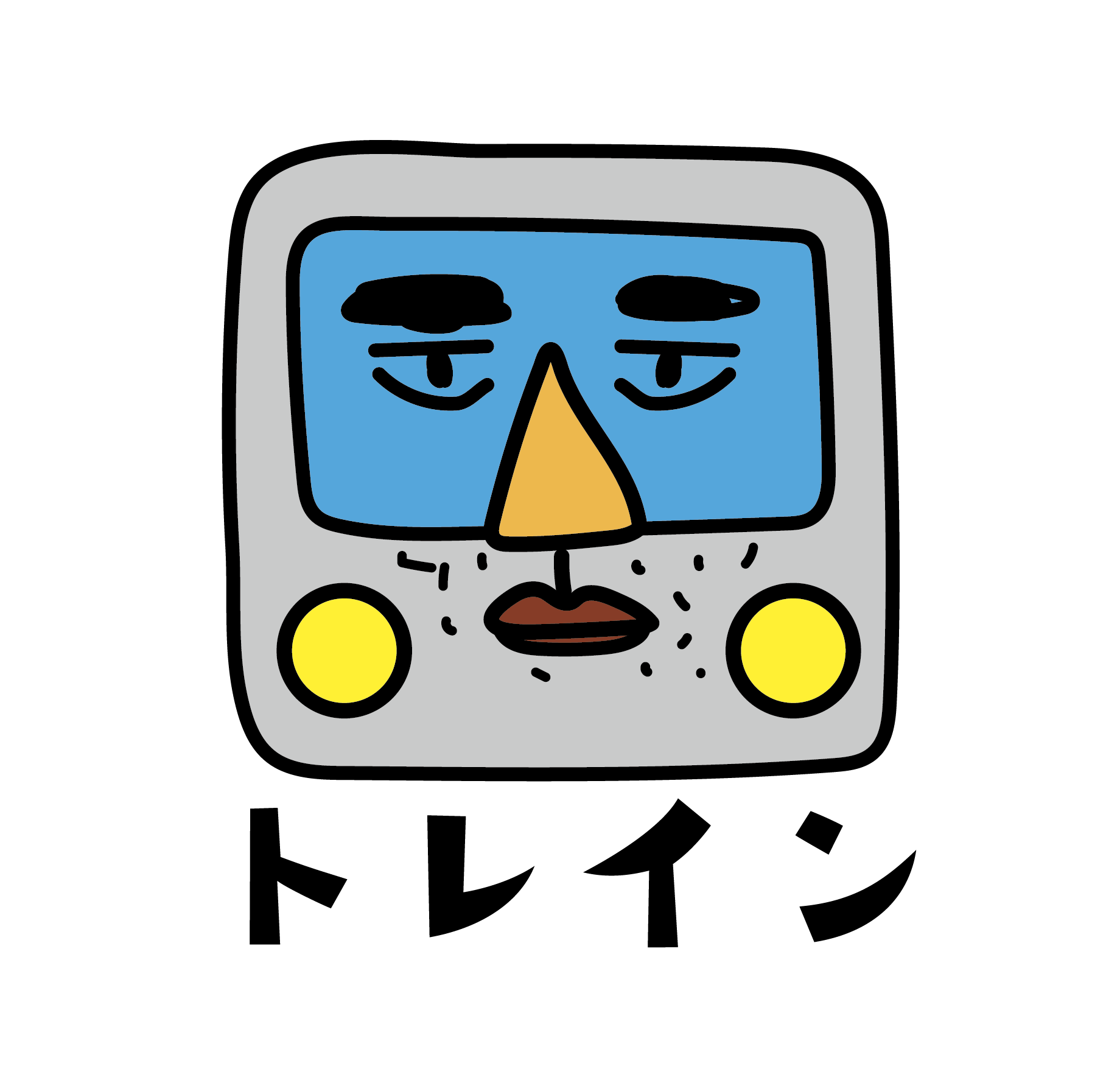
え?コップ?なんでコップ?
(比喩表現が理解できない)
でも、彼らも感情があるので、未解決の感情や不満はどんどん蓄積されているわけです。
その末に起きる犯罪行為だというわけです。
誤解を招かないように書きますが、
宮口先生は犯罪者を擁護するわけでも、
ましてや犯罪を仕方なしとしているわけでもありません。
あくまで、知能問題がある子の犯罪に至るまでの背景を描くことで、
必要な支援が行き届いていない社会への警鐘を鳴らしたいのだと
大福は受け止めました。
境界知能って一昔前の基準では知的障害者ですからね。
障害者の比率が高くなってしまって支援が行き届かないからと
支援の枠から外されてしまった領域の人たちです。

障害者と健常者のエアポケット的な境界知能者!
軽度知的障害者や境界知能者の支援はプロでも難しい!
主人公の六麦先生も少年院の先生も、彼らの更生のためにすごく寄り添った対応をされているのが意外でした。
少年院で働くってすごいことなんだなと思いました。

私にできるかと言われたら、できない。
手探りながらも常に寄り添いをし続けて、それでやっと更生することができて、社会に帰ったと思ったら、また戻ってきてしまう人も多いそうです。
そんな支援のプロである人たちでも、彼らを支える難しさを感じているわけで。
ましてや、一般人の我々がですよ。
パートナーの知能問題がわかったからっていって、そこから一人で抱えていくなんて到底無理ゲーだよなって改めて思いましたね。
現在のところ、境界知能に対する社会の支援は特にないのですが、
「支援いるよ!本人だけじゃなく支える家族やパートナーだってめっちゃしんどいわ!」って思いました。
だって、知能問題を抱えている人を支えるって本当に大変なんです!
支援者がいても当事者の人生は超ハードモードなのに変わりありませんが、
でも支援者がいるからこそ、彼らはなんとか社会で生きているわけです。
作中で好転していく少年・少女には、本人が信頼できる良い支援者との出会いがありました。
それだけ支援者の存在自体が尊いことでもありますが、支援は常にしんどさとの二人三脚です。
本人は「頑張りたい」と思っていても、知能問題ゆえに「頑張れない人」なわけで、その頑張れない分を背負って頑張っているのは、共にいる家族やパートナーなわけですから…

当事者・支援者ともに救いあれ
とにかく、一人で抱え込むのはやめよう!
知能問題を抱えている当事者と、知能問題がある人を支えている人の全員に伝えたい。
とにかくアウトプットしていくことが大事だと。
行政やNPO、民間企業、SNSでもなんでもいいから、
まずは支援を受けられる場所や聞いてくれる場所を見つけて
胸のうちを外に出さないことには始まらない。
当事者の人は、生きづらさを理解して支援してくれる場所を探すことが結果的に生きやすくなると思いますが、頼る先はなるべく行政や団体などのプロを求めたほうがいいと思います。
正直、何もわからない素人が背負う問題としては荷が重いことでもあるし、人によっては耐えられなくて相手を潰してしまう危険があると思います。
また、発達検査や知能検査、ストレングスファインダーなどの検査を活用して
自分の特性をよく理解することも大事だと思います。
できること・できないこと・得意なこと・苦手なことが
普通の人よりも極端に解離があるかもしれないので。
元夫トレインも、長い間、あまり適性のない仕事をやっていました。
特に向き不向きが色濃く出やすい発達障害グレーゾーンと(ほぼ)境界知能をあわせて持っているトレインなので、向いてない仕事では本当に評価が得られませんでした。
頑張っても全てが裏目にでるので、本人は苦しかったことでしょうが、
大福は家庭を守る上で、酷いとばっちりを長期間受けまくってストレスで心身ともにおかしくなりました。

今思い返しても、へそで茶が沸くレベルには怒りが蘇ってきます。
更に、離婚前にいきなり会社を辞めて無職になった期間があるのですが、
無職期間は日雇いで、毎日違うバイトに行きだしまして…
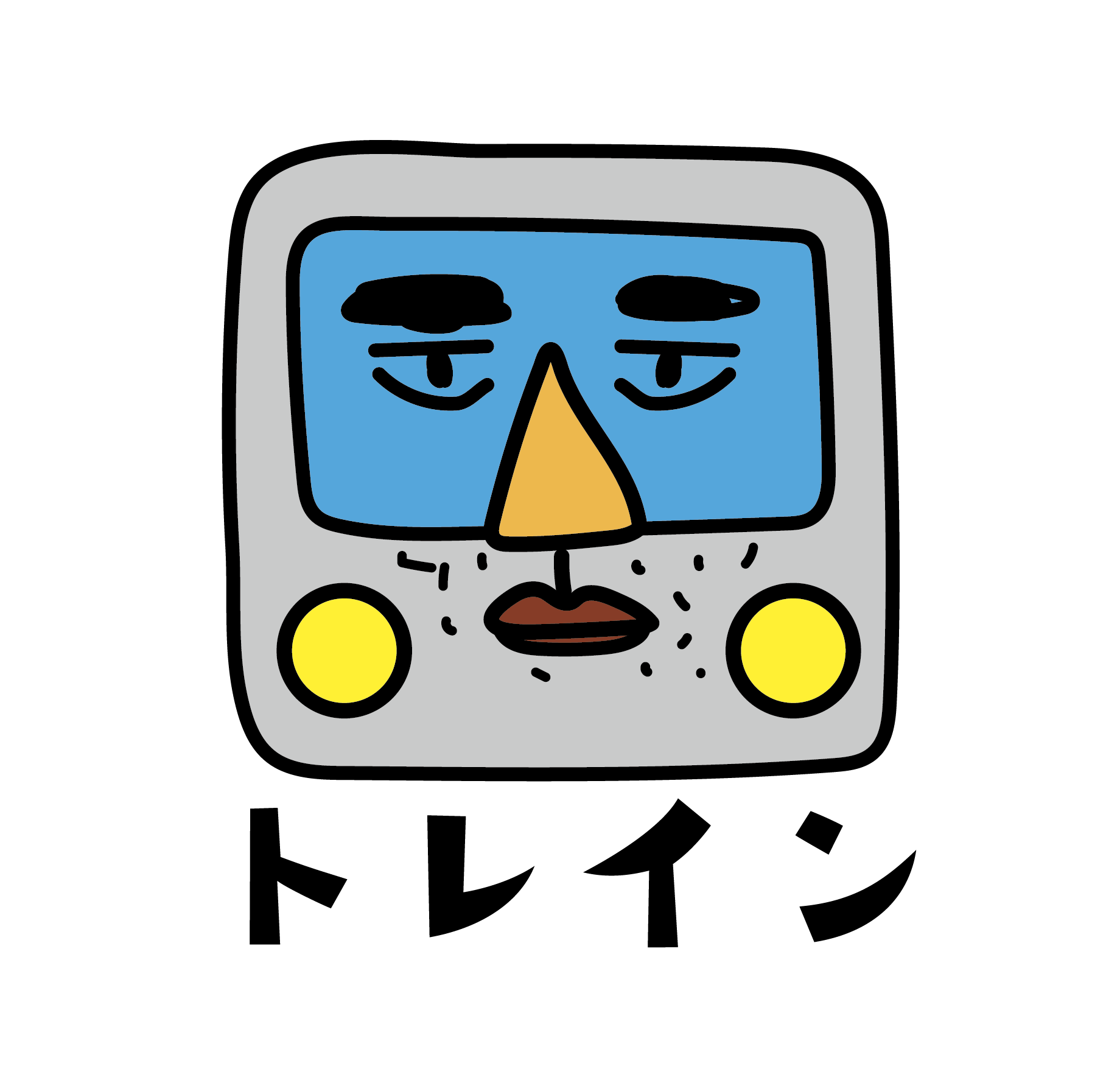
今日はゴミ処理場に行ってくるよ!

え?バイト?
(とりあえず)いってらっしゃい
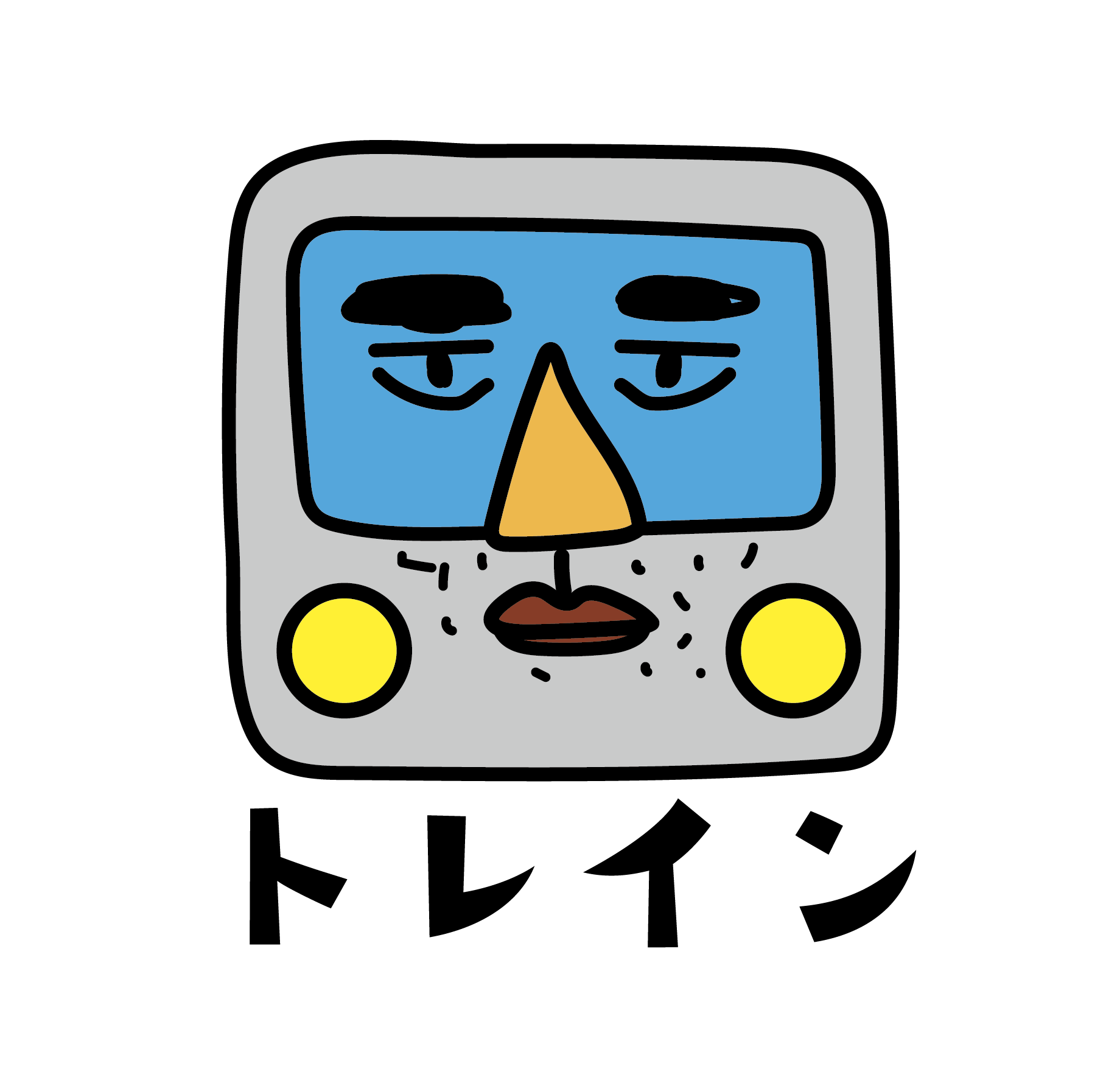
今日は深夜にお酒の配達をやってくるよ!

またバイト?
いや、就活は?
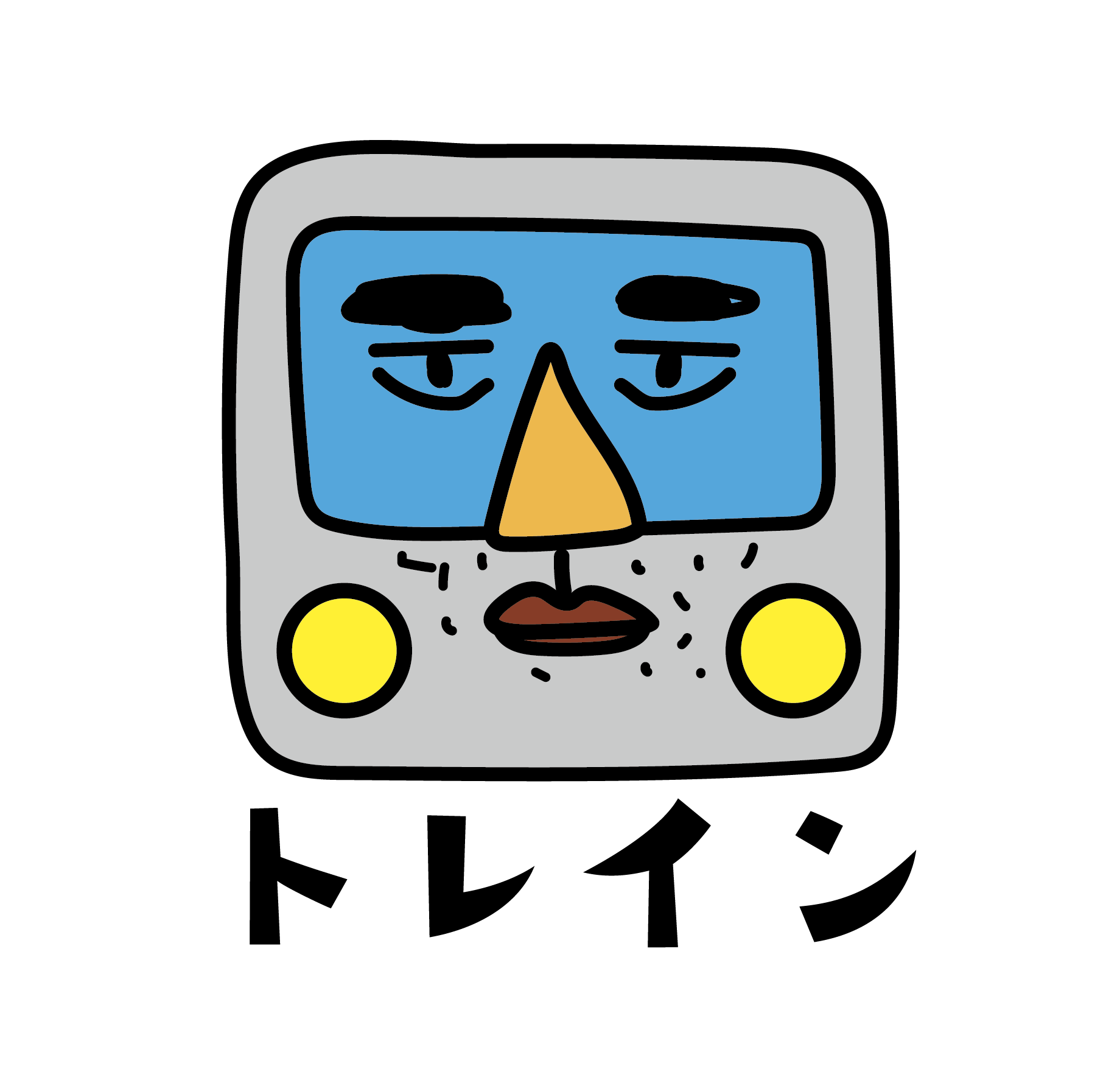
今日は倉庫作業にいってくるよ!

ちょとまて。
就活してくれよ
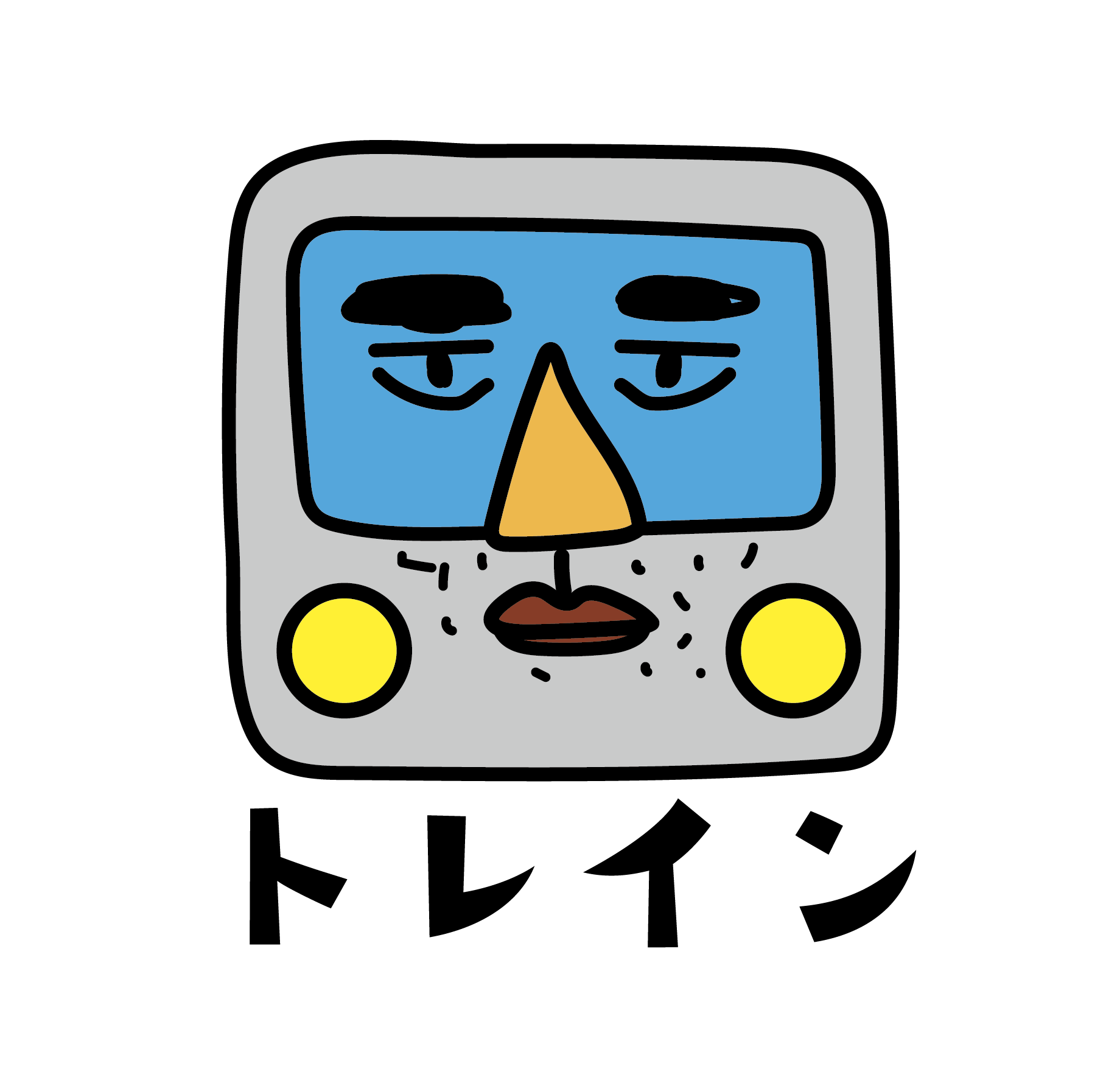
今日はファミレスに行ってくるよ!

いい加減に
就職しろよ!(怒)
こんなかんじで「キッザニアbyトレインVer.」のごとく、色々な職業体験を繰り広げていました。
本人が楽しくてやってたことなので、数ヶ月続いてましたね。
日雇いバイトで得られる給料では生活費に全く足りず、家計は火の車。
当の本人はそんなことお構いなし!他者目線のない発達障害グレーゾーンなので、毎日イキイキしてましたよ。

大福は毎日、◯ねばいいのにって思ってました♡
ただ、結果的にですが、その日雇いバイトたちの中から
「好きで、仕事としても適性がある」職業を自力で見つけ出しまして、
今はその仕事に没頭しています。
一度パズルのピースがハマると、発達障害の特性である過集中が発揮され、
今度は仕事人間になりました(無職より1000倍マシ)。
この極端さも発達障害と境界知能の合わせ技だなとも思っているので
ある日突然コロっと変わってしまうのではないかと常に懸念はしています。
また、もし特に支えてくれる人がいる場合は、
相手がどれだけ自分の人生のために手を尽くしてくれているかを、
分からないなりに考えてみてほしいなと思います。

わかるまで考えてほしいですけどね
支えている側の人には、
定期的に「一定の距離をとる」タイミングを設けてほしいと思います。
ずっと一緒にいたら疲れてしまうし、
相手のために自分の人生の大部分を割いているわけなので、自分を守るためにも。
知能問題のある人の言動は、認知が弱いために一貫性がないのですが、
こちらが疲れていたりすると判断も鈍ってしまい、
結果的に振り回されてしまったりすると思います。
冷静さや判断力を保つためにも、相手との境界線、しっかり意識してほしい。
六麦先生の対応が、境界線を保つ視点として役に立つなって大福は思いました。
参考情報
大福はトレインとの間に子供が1人いますが、トレインや自分の特性から、常に子供の発達や知能は気にかけています。
今回漫画を読んで、境界知能のこどもについて更に知りたくなり、宮口先生が話している内容を見つけて読むことができました。
ポイントだけまとめますので、なにかの参考になればと思います。
・境界知能は、同じ年齢の子供の8割程度の知能になる
・認知機能が弱いと、感情や行動のコントロールがうまくできない
・小学校2年生くらいからまわりとの差がでてくる傾向がある
原作の小説はこちら
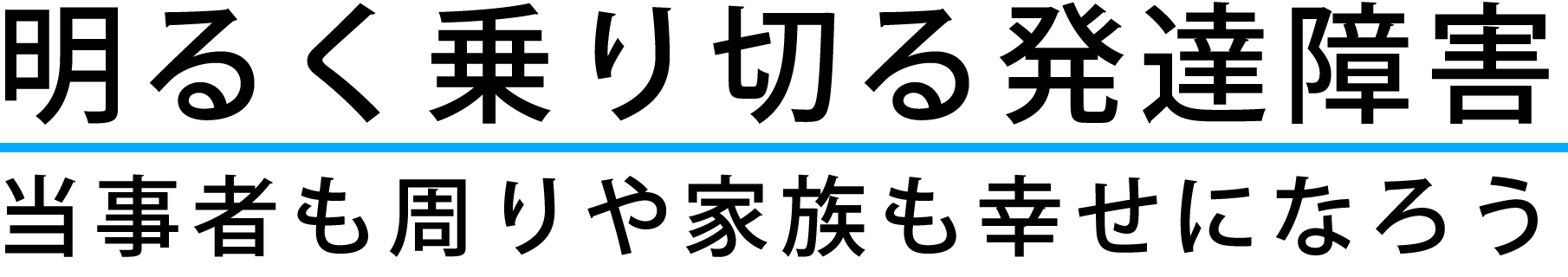



コメント