今日も唇荒れが治らない大福です。
先日、愛しい我が子「大福Jr.ちゃん」の耳の中に黒い点があるのを発見しました。
「ん?ほくろ?いや違う・・・汚れかな?かさぶたかな?」とよくよく観察すると、どうやらほくろでも汚れでもかさぶたでもない。綿棒でこすってみても、全く取れる気配もないし、なんだか根っこのようなものがある気がする。
結論としては大福Jr.ちゃんに「粉瘤(ふんりゅう・別名アテローム)」ができてしまいましたぁ・・・(ショック)
大福は、大福Jr.ちゃんの耳の症状を調べていくうちにだんだん「耳瘻孔」と「粉瘤」の違いがよくわからなくなって混乱してしまいました。
そこで今回は、同じように違いについて混乱している人や「耳瘻孔」や「粉瘤」がそもそも何なのかを知りたい人向けに、耳瘻孔と粉瘤について、一般人目線で専門的な用語は極力使わずにまとめてみました。大凡こういうことなんだなというポイントはわかってもらえると思うので、ぜひ参考にしてみてください!
耳瘻孔(じろうこう)とは
耳瘻孔は、母親の胎内で育つ際に、耳の組織の一部がうまく結合することができずに出来上がってしまった耳の奇形の1つです。耳の一部に穴ができ、穴の中には袋上の皮が形成されています。
100人に一人の割合という人や、20人に1人の割合という人もいるなど、医師によって割合にばらつきはありますが、この数字からみても結構な数の人が耳瘻孔を持っているんだなという印象を大福は抱きました。
そもそも、瘻孔(ろうこう)自体は、耳にできれば「耳瘻孔」ですが、全身どこにでもできる可能性があり、よくある奇形です。
耳瘻孔の原因は、遺伝による影響もあるようです。
特に、耳瘻孔を持つ親の子供は、耳瘻孔が遺伝する可能性が高くなるようです。
ちなみに、大福の元夫が先天性耳瘻孔です。
耳瘻孔は、通常時はとくに痛くも痒くもありません。
何も異常がない場合は、そのまま放置していても問題ありません。
ただし、細菌感染のリスクは常にあり、注意が必要にはなります(日常生活で制限を設けるほどのことはありません)。
粉瘤(ふんりゅう・アテノーム)とは
皮脂や垢などの汚れが表皮の下に溜まってしまう良性の「できもの」です。
黒いほくろのように見えたり、白っぽく盛り上がったりするのが特徴です。
耳瘻孔のように中心に穴があるタイプのものと、穴がないものがあります。
耳瘻孔か粉瘤かはエコーをつかって診るようですが、炎症が起きてしまうと耳瘻孔か粉瘤かの見分けは、とてもわかりにくいようです。
大福Jrのケースでは、粉瘤が少し溜まっている関係で黒いほくろのように見えるのですが、よく見ると中心に穴があって、ちょっと盛り上がっていました。
粉瘤も瘻孔と同じく、全身のどこにでもできる可能性があります。多いのは耳、背中、お尻、首などです。
耳瘻孔と粉瘤の共通点
完治するには手術を受けるしかなく、手術以外で、炎症が起きた場合は対処療法として、抗菌剤・抗生剤を服用することが多いです。膿がひどく溜まっている場合は注射で抜くこともあります。
手術では、局所麻酔による「切開手術」や「くり抜き手術」を行います。
病院によっては、受診当日に即日手術の対応をとってくれる病院もあり、基本的には日帰り手術です。
粉瘤になった会社の同僚は「なんだか脇が痛いな」と思って病院を受診したらすぐ手術になって、10分程度で終わって帰宅したと言っていました。
耳瘻孔や粉瘤の部位にやってはいけないこと
以下の3点、全て細菌感染のリスクを高めてしまうのでご法度です。
- 自分で汚れを穴から押し出してしまうこと
- 毎日消毒すること
- 部位を気にして触りすぎること
大福は、大福Jr.ちゃんの耳を綿棒でこすったことを激しく反省しました。また、粉瘤の塊が穴から勝手に取れたケースもあるようですが、その場合は取れた穴から細菌が入る可能性があるので一度先生に見てもらったほうが良さそうです。
病院は何科に行けばいいの?
「皮膚科」か「形成外科」です。
「耳鼻科」でもとりあえず観てくれるようですが、本来は皮膚科か形成外科の領域のようです。
大福は、とりあえず近所の皮膚科に駆け込みましたが「手術するなら形成外科の紹介状を書く」と言われたので、即手術を希望であれば「手術の可能な形成外科に行く」のが一番スピーディではあります。とりあえずの様子を診てもらうだけ、などであれば「皮膚科」でも対応可能、そんな感覚でいいと思います。
こどもの耳瘻孔・粉瘤はどう考えればいいの?
大福が聞いた医師の話では「耳瘻孔や粉瘤は、症状が特にないうちは”ほくろ”と同じような位置づけで考えてもらっていいです。ほくろは、すぐに何かしないといけないものではないし、毎日気にして過ごしたりはしないけど、存在はしていますよね。それと同じ感覚で問題ありません。ただ、ほくろと違うのは両方とも細菌感染のリスクがある点なので、耳瘻孔も粉瘤も早めに手術で完治させておくに越したことはありません」とのことでした。
本人に「耳瘻孔(粉瘤)を取りたい、治したい」という強い意思があれば、早くて9歳か10歳くらいから局所麻酔でも対応できるそうですが、医師の考え方と、子供の性格や気質を見つつ進めるのが基本のようで、幼い子どもにいきなり全身麻酔で手術を行うことはありません。局所麻酔ができるようになる年齢まで待って手術するケースがほとんどです。中には何も支障がないからと放っておく人も多いようです。
子供の耳瘻孔や粉瘤に気づいたら
- 「痛がっていないか」「痒がっていないか」「耳を気にしていないか」を確認。
- 痛がっているようなら、炎症を起こしている可能性が高いので、早急に病院へ。
- 特に痛がる様子も痒がる様子も耳を気にしている様子もないようであれば、緊急性はありません。
- 耳の状況を把握するためにも、一度は受診しておきましょう。先生から様子見でいいなど方針が出ると思うので、医師の方針に従って経過を見守りましょう。
日頃のケア
子供も大人と同様に「炎症が起きない限りは、特になにもしなくていい」です。あまり気にしていじりすぎるのが、一番良くないそうなので、目視で状態を確認する程度にしてくださいとのこと。
小児科などでもらった抗生剤は耳瘻孔・粉瘤の炎症にも効く?
ウィルス性の風邪などを引いた際に抗生剤が処方されることもありますが、その抗生剤は耳瘻孔や粉瘤の炎症にも効くのか気になって医師に聞いてみましたところ以下の回答でした。
「抗生剤を飲めば基本的に全身に効き目があるので、炎症がどの程度強く起きているかと抗生剤や抗菌剤の強さも関係ありますが、耳瘻孔や粉瘤の炎症にもその薬の強さでは効くとは思います。ただ、抗生剤は、一度飲みだすと、きっちり飲みきらないと耐性がついて返って効果が出なくなってしまうこともあるので、中途半端な飲み方はやめてください」
休日や夜間など、病院がやっていない時間帯に痛がったりした場合の応急措置程度にはなるのかなぁと思って聞いたのですが、乱用はやめたほうが良さそうですね。
痛みはカロナールなどで一時的にしのぎつつ、すみやかに病院に行くしかないなという感じです。
いつでも対応できる体制が大事と受け止めたので、夜間対応の病院なども調べておく必要がありそうです。
【参考】発達障害グレーの大福元夫の事例
発達障害グレーゾーンバリバリの元夫が耳瘻孔をこじらせた時のことを書きます。
耳瘻孔に限らず、どの病気も同じような対応を取るんだろうなと思ったので、参考までに。
数年前ですが、元夫の耳瘻孔が細菌感染して、耳の根本に膿が溜まり、ぷっくりと大きく膨れ上がって大変なことになっていました。
相当痛かったようで、本人は抑うつ状態になり(単純に具合も悪かったのですが)ASDの自閉傾向が強くなってコミュニケーションはもちろん成立しないですし、想定外の自体にキャパシティを超え、現実逃避をしようとする傾向が強かったです。
耳瘻孔の炎症が酷いと手術もできないようで、まずは膿を注射で抜きながら抗生剤で症状を鎮静させる対処療法を受けていました。
熱もあり、毎日病院に通って点滴を受けなければならず、落ち着くまでに1週間以上かかりました。
しかし、ここからが大事なポイントで、一度症状が落ち着くと、元夫は「先延ばし特性」と「忘れてしまう特性」によって、あんなに痛い目を見た経験も全く活かされないまま治療を放置してしまいました。
「手術が怖い」というのが本音にあるようですが、とにかく「見て見ないふり」を現在も続けております。よって、耳瘻孔は完治していません。大人の発達障害の人は「実際に目の前に起きていない問題」は「問題がない」ことと同じように認知してしまい、問題を直視しないで放置し続けてしまいます。元夫も、また耳瘻孔の炎症が起きてひどい目に遭うまでは、すっかりなかったことになってしまっているので、大福はもう離婚しているし、何も言いません。
「言ってくれる人がいるうちが華」なのですが、底づき感を本人が体感するまでは変化はないと思っています。
まとめ
- 耳瘻孔も粉瘤も細菌感染による炎症が起きていない限り緊急性は低く、放置しても問題はありません。
- 炎症が起きるリスクが常にあるので、「痛い・痒い」などの違和感が出たらすぐに形成外科か皮膚科へ行きましょう(事前準備として休日・夜間対応の病院も調べておきましょう)。
- 子供は、局所麻酔で手術ができるようになるまでは、炎症がおきたら抗生剤や抗菌剤を服用して症状を落ち着かせて様子を観るのが原則(医師や症状と相談しながら進める)。
- 将来のリスクを踏まえると放置し続けるのは危険!しっかり根治が望ましい。
「耳瘻孔・粉瘤」を謳っている病院が全国にあるので、困っている方は形成外科で「耳瘻孔・粉瘤」について取り上げている病院を目安に選ぶといいかもしれません。
参考にしてみてくださいね!
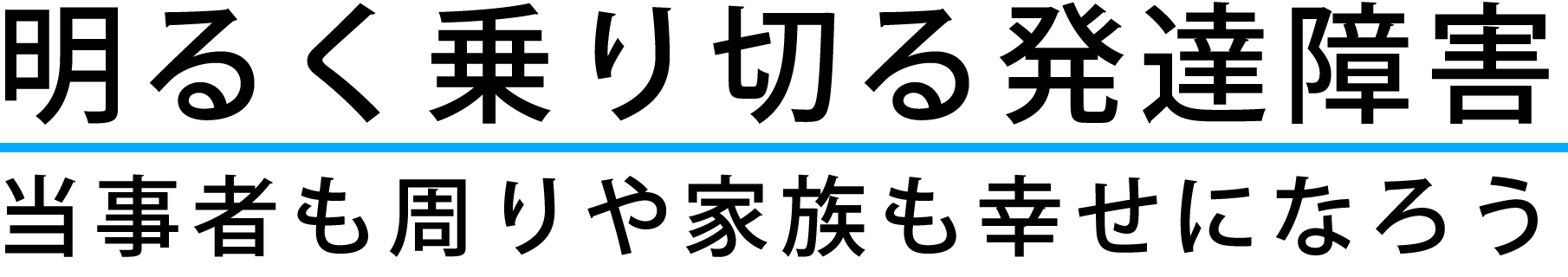



コメント